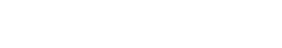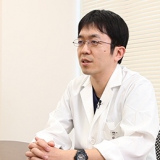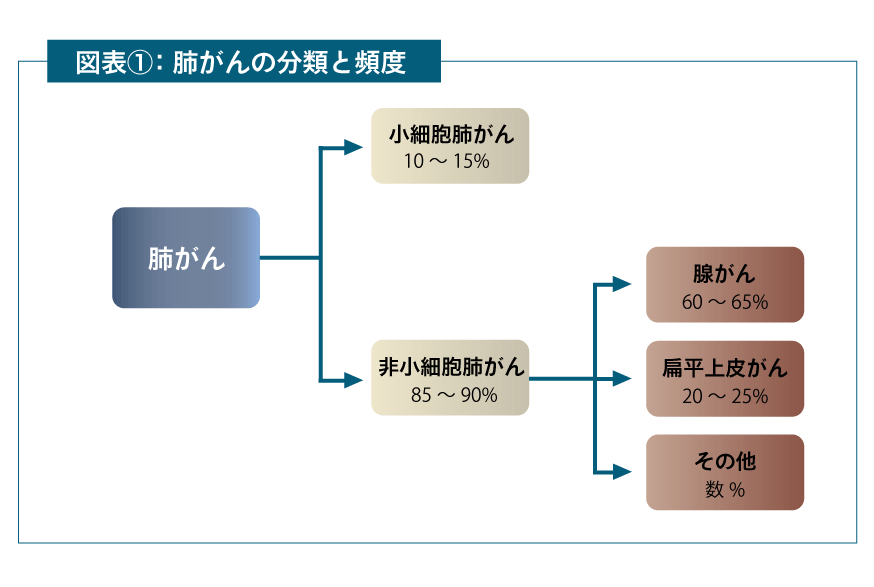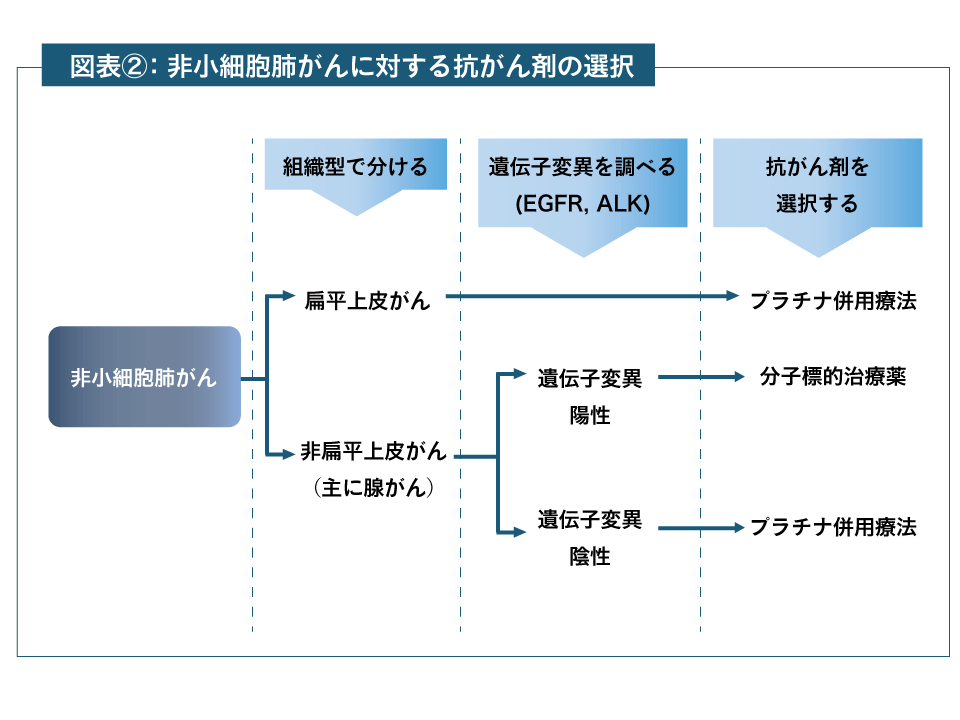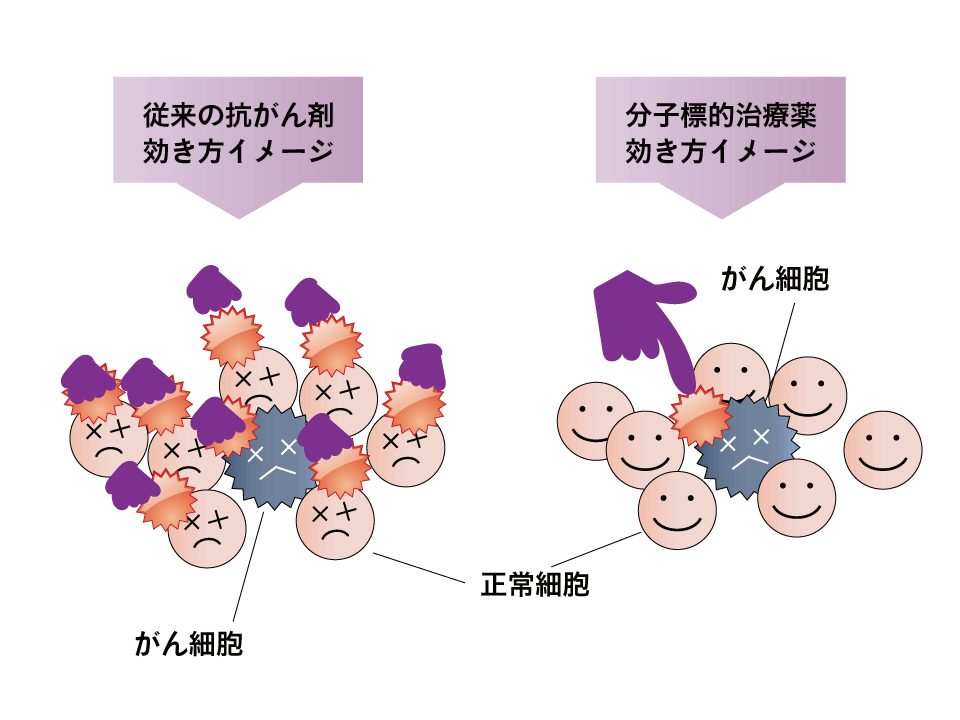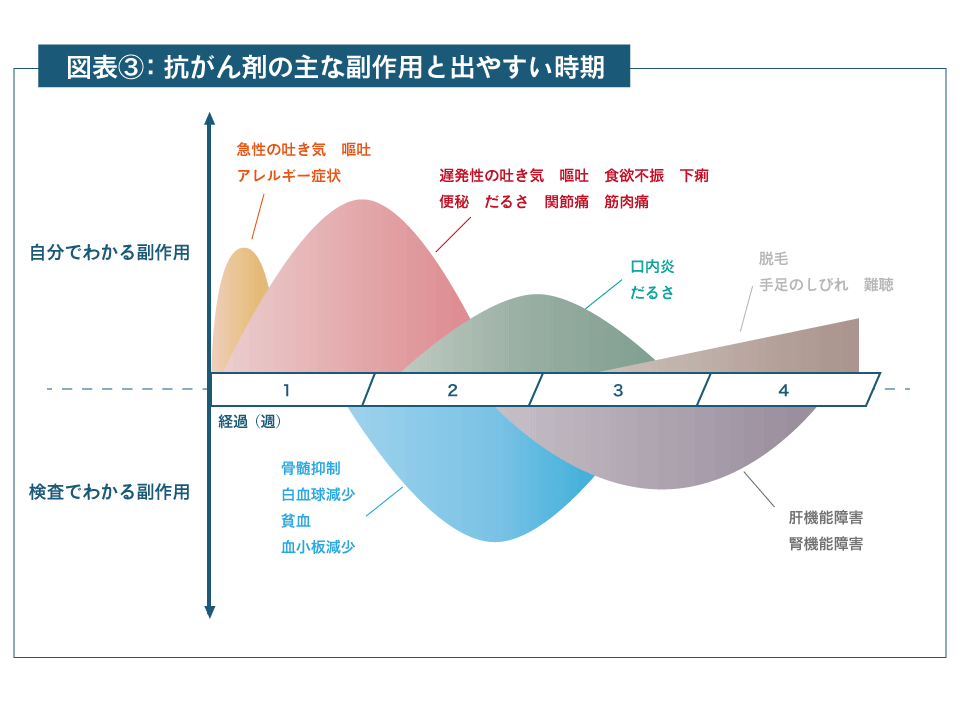非小細胞肺がんの化学療法 肺がんの治療法
プロフィール
非小細胞肺がんとは?
肺がんは「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2つに分類されます。
内視鏡検査や手術で採取してきたがん細胞を顕微鏡で見ると、肺がんの細胞は多彩な顔つきを持っていることが分かります。こういったがん細胞の顔つきのことを「組織型」と言います。さらに非小細胞肺がんは「腺がん」、「扁平上皮がん」などに細かく分類されていきます。
頻度としては、現在、日本人の肺がん患者さんの8割以上が非小細胞肺がんに分類されます。このように肺がんを「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2つに分ける理由は、両者が異なる性質を持っているからです。具体的には、非小細胞肺がんは小細胞肺がんに比べ、進行がゆっくりである一方で、抗がん剤や放射線がより効きやすいのは小細胞肺がんの方です。今回は、非小細胞肺がんに対する抗がん剤治療について解説します。
抗がん剤の適応について
非小細胞肺がんでは、病期の進行度に応じて、手術や放射線治療と抗がん剤を組み合わせたり、あるいは抗がん剤単独での治療を行います。
Ⅰ期もしくはⅡ期で手術を行った患者さんに対して、術後にがんが再発するリスクを下げる目的で行われる抗がん剤治療は、「術後補助化学療法」といわれます。
Ⅲ期の患者さんでは、放射線治療と併用して抗がん剤治療が行われ、「化学放射線療法」と呼ばれます。
一方で、Ⅳ期の患者さんに対しては、抗がん剤単独での治療になります。
肺がんにおけるⅣ期というのは、具体的には診断された時点で肺以外の臓器に転移がある患者さん、がん細胞により胸の中や心臓の周りに水が溜まっている患者さんなどが相当します。ここからはⅣ期の非小細胞肺がんに対する抗がん剤治療について解説します。
術後補助化学療法
手術の後に再発する可能性を下げる目的で行う抗がん剤治療
化学放射線療法
ステージ3に分類される患者さんで放射線と併用して行う抗がん剤治療
進行肺がんに対する抗がん剤治療
放射線との併用治療が難しいステージ3、およびステージ4の肺がん患者さんに対する抗がん剤治療。
※肺がんにおけるステージ4
・診断された時点で肺以外の臓器に転移がある患者さん
・がん細胞により胸の中や心臓の周りに水が溜まっている患者さん
抗がん剤治療を行う目的
Ⅳ期の非小細胞肺がん患者さんに抗がん剤を使う目的について解説します。
Ⅳ期の非小細胞肺がん患者さんの場合、がんは肺以外の臓器にも広がっているため、全てのがん細胞を手術や放射線で治療することはできず、完治が難しいと考えられます。
このような患者さんには、全身のがん細胞に対して効果のある抗がん剤治療を行います。
Ⅳ期の非小細胞肺がん患者さんに対する抗がん剤治療の目的は2つ挙げられます。
ひとつめは、がんの進行を抑えてより長生きできるようにすることです。
また、がん細胞の存在によって肺がんの患者さんは様々な症状を自覚することがあります。
そこで抗がん剤によって腫瘍を小さくすることにより、がんに由来する様々な症状を和らげ、患者さんのQOLを維持すること。これが抗がん剤治療のふたつめの目的になります。
抗がん剤治療の目的
・がんの進行にブレーキをかけて、元気により長生きできるようにすること
・がんに由来する様々な症状を和らげQOLを維持すること
どのように抗がん剤を選んでいくのか?
近年、非小細胞肺がんに対して効果の高い抗がん剤が相次いで登場してきたため、抗がん剤の選択肢も増えました。
以前は非小細胞肺がん患者さんでは初回に「プラチナ製剤」と「第3世代抗がん剤」の2種類を用いて治療するのが標準的な治療とされ、腺がんや扁平上皮がんなどの組織型による差はありませんでした。最近になり組織型によって効果が異なってくる抗がん剤が登場し、またがん細胞の中に遺伝子異常を有している患者さんに対してすぐれた効果を発揮する「分子標的治療薬」といわれる飲み薬も登場してきました。このような「分子標的治療薬」が効きやすい遺伝子を持った患者さんは、主に腺がんなどの扁平上皮がん以外の患者さんで多くみられます。そこで、現在では非小細胞肺がんの中でも組織型が扁平上皮がんなのか、それとも扁平上皮がん以外の組織型なのかによって治療法が分かれます。さらに扁平上皮がん以外の患者さんにおいては、「EGFR」、「ALK」という2つの遺伝子検査を行い、細胞内の遺伝子の状態を調べます。こうして「分子標的治療薬」の効果が期待できる患者さんを選択して行きます。一方で、遺伝子検査が陰性や扁平上皮がんの患者さんでは、従来と同じく「プラチナ製剤」と「第3世代抗がん剤」の2種類の併用治療が選択肢になります。
このように、患者さんの組織型や遺伝子検査の結果に加え、年齢や全身状態も考慮して、患者さん1人1人に最も適した抗がん剤を選んでいます。
分子標的治療薬とは?
分子標的治療薬とはがん細胞内にある遺伝子の異常を標的として開発された内服の抗がん剤です。分子標的治療薬の登場により非小細胞肺がん、特に腺がんの治療成績は非常に向上しました。
非小細胞肺がんの一部では「遺伝子変異」と呼ばれるがん細胞内の遺伝子異常が存在することが知られており、この遺伝子変異よって肺がんが発生し進行していくがことが知られています。具体的には「EGFR遺伝子」や「ALK遺伝子」などの遺伝子変異が知られています。これらの遺伝子変異は煙草を吸わない人や若年の患者さん、腺がんの患者さんなどで見つかることが多く、またEGFR遺伝子変異については欧米と比べて日本人で遺伝子異常を持った患者さんが多いと言われています。
そこで、これらの遺伝子変異を持ったがん細胞を標的として開発された抗がん剤が分子標的治療薬です。
分子標的治療薬は飲み薬でありながら、がん細胞に対して非常に高い効果を示します。
現在、日本では扁平上皮がんを除く非小細胞肺がんの患者さんについては、最初にEGFRやALKなどの遺伝子変異の検査を行い、もし変異が見つかり分子標的治療薬の効果が期待できる場合には初回治療で分子標的治療薬の投与を行うことが推奨されています。
これらの分子標的治療薬は現在も開発が進んでおり、今後さらに治療の選択肢が広がる可能性もあります。
抗がん剤にはどのような副作用があるのか?
抗がん剤治療を続けていく上で、最も重要なことは効果と副作用のバランスです。
どんなにがん細胞に対して優れた効果を示す薬剤でも、副作用が強く出てしまい患者さんの体力が大きく消耗されてしまうようでは良い治療とは言えません。
抗がん剤治療中は効果のみでなく副作用の面も重要視していますので、どのような副作用が出て、日常生活にどれくらい影響しているかなども私たちに伝えていただきたいと思います。
抗がん剤の副作用は大きく、「自分で感じる副作用」と「検査でわかる副作用」の2つに分類されます。「自分で感じる副作用」としては、食欲不振や吐き気、下痢、体のだるさなどが代表的な症状です。これらは概ね投与2週間以内に見られやすい副作用です。
これらの副作用に対しては、飲み薬や点滴によって適時対処していきます。
ふたつ目の「検査でわかる副作用」としては、肝臓や腎臓などの内臓機能の異常や骨髄抑制といわれる副作用で、血液検査によって分かる副作用です。
この中でも注意が必要なものとして骨髄抑制が挙げられます。
具体的には白血球の減少や、貧血、血小板の減少などです。白血球の減少により体の免疫力が低下するために感染症を合併する危険性が高くなります。また貧血の進行や血小板減少に対しては、その程度によって輸血を行う場合もあります。
外来通院での抗がん剤治療も可能に
患者さんに新たな抗がん剤を始める場合、1回目の治療は入院で始めて副作用などを注意深くみることが多いです。1回目の投与で副作用などが問題なければその後は外来で投与できる抗がん剤も多くあります。
以前は肺がんに対する抗がん剤治療は専ら入院で行っていましたが、近年では吐き気止めなどの副作用対策の薬が進歩し、分子標的治療薬などの飲み薬などの選択肢も増えました。
これらの治療の進歩により、最近では外来での治療も普及しています。